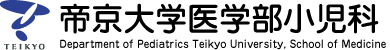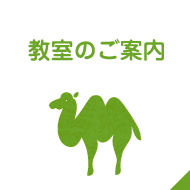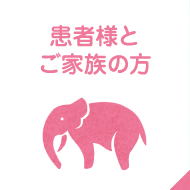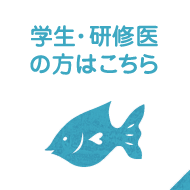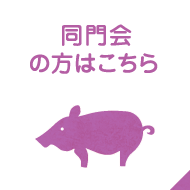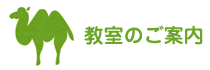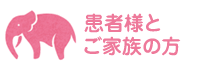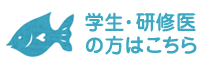神経班の紹介

特色
子どもたちの病気の中で、神経発達に関連する病気は頻度も高く大勢の方が受診されています。神経外来では、脳、脊髄、末梢神経、筋肉などと関連する疾患が対象となりますので、てんかん、脳および全身の先天異常症、神経筋疾患、先天性代謝異常症、神経系の感染症や免疫疾患、知能面の問題、自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害などの発達の問題、脳性麻痺、神経系の進行変性疾患、脳腫瘍・脊髄腫瘍など、病気は多岐にわたります。
小児神経の専門医療機関として、これらの広い領域の先端医療を行える体制をとっており、希少な疾患についても経験のある専門医が診療に当たっています。必要に応じて、小児専門の耳鼻科・眼科などの他科との連携を行ったり、当科の遺伝外来とともに診断やその後のフォローアップを行ったりします。また、当院は総合周産期母子医療センターの役割を担っているため、新生児期に集中治療を受けた子ども達の包括的なフォローアップにも注力しています。
神経領域の特殊検査として、脳波検査を含む神経生理検査、MRIやSPECTを含む頭部画像検査などの専門的な検査を行っています。特にてんかんについては、小児期発症の患者さんが多く受診しており、難治てんかんについては長時間ビデオ脳波同時記録や頭部画像検査を用い、他施設とも共同して総合的な診療を目指しています。また、発達障害や知的障害については、原因となる疾患の精査を行い、正確な診断のもとで適切な療育を行うことができるよう、当院の心理外来や地域の療育機関や教育機関との連携に努めています。
一方、小児救急領域における神経疾患への対応も重要で、けいれん発作や意識障害などについて、専門的治療を行う体制をとっています。また、重症心身障害児など、神経領域の基礎疾患を有する子どもの急性増悪時への対応にも努めています。
対象疾患
- てんかん
・良性家族性新生児・乳児てんかん、早期ミオクロニー脳症、大田原症候群、ウェスト症候群、レノックス・ガストー症候群、ドラベ症候群、中心側頭部棘波を示す良性てんかん、小児後頭葉てんかん、欠神てんかん、若年ミオクロニーてんかん - 熱性けいれん
- 周産期の脳障害
・脳室周囲白質軟化症、新生児仮死後遺症など - 発達の問題
・知的障害、自閉スペクトラム症、ADHDなど - 片頭痛
- 周期性嘔吐症
- 先天性代謝異常症
・ミトコンドリア異常症、ライソゾーム病、神経セロイドリポフスチン症、有機酸代謝異常症、アミノ酸代謝異常症、銅代謝異常症など - 神経系の感染・免疫疾患
・急性脳炎・脳症、髄膜炎、先天性感染症、急性散在性脳脊髄炎、多発性硬化症など - 筋肉の疾患
・デュシェンヌ型/ベッカー型筋ジストロフィー、筋強直性筋ジストロフィー、先天性ミオパチーなど - 末梢神経などの疾患
・遺伝性運動感覚ニューロパチー、ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、重症筋無力症など - 神経変性疾患
・大脳白質変性症、脊髄小脳変性症など - アンジェルマン症候群、レット症候群など
- 水頭症、脳回形成異常、二分脊椎など
- 神経皮膚症候群
・結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群、神経線維腫症など
結節性硬化症診療連携について
当院では、小児科、脳神経内科、脳神経外科、呼吸器内科、泌尿器科、皮膚科、眼科等の複数診療科による結節性硬化症診療連携を行っています。新生児期から成人まで、結節性硬化症の多様な症状に対する専門的医療を提供しています。
また、定期的なカンファレンスを実施し、複数の合併症を持っている患者さんが各診療科を受診しやすいよう、診療科の垣根を越えた連携を目指しています。
当院で主に治療できること
- てんかん
結節性硬化症患者さんにはてんかん発作がみられることがあり、その症状に応じて治療を行います。特に、結節性硬化症に伴うウェスト症候群(点頭てんかん)へのビガバトリンの有効性は認められており、当院でも治療を行っております。現在、小児科を中心に、難治性てんかんへの治療の取り組みを行っています。 - 腎血管筋脂肪腫(AML)
結節性硬化症に伴うAMLに対しては、エベロリムスの服薬や外科的治療を検討します。泌尿器科を中心に治療方針を決定します。 - 肺リンパ脈管平滑筋腫症(LAM)
結節性硬化症患者さんに発生するLAMは比較的少ないですが、成人女性に多く見られます。初期は無症状のことが多いですが、進行すると呼吸困難が悪化する場合があります。シロリムスの内服などの治療法があり、当院では呼吸器内科が対応します。 - 皮膚症状
顔の血管線維腫(赤みを帯びたボツボツとしたもの)や爪周囲の線維腫が生じることが多く、日常生活上の困難度や美容面を考慮して、皮膚科でシロリムスの外用薬等による治療を受けることができます。
連携診療科の連絡先
初めて受診を希望される患者さんは、中学生以下の方は小児科、それより年長の方はお困りの症状に応じて、下記の診療科宛にかかりつけ医から紹介状(診療情報提供書)をもらって、各科窓口までお問い合わせください。
| 診療科 | 連絡先 |
|---|---|
| 小児科 | 小児科外来(小児科の神経外来を予約して下さい) |
| 脳神経内科 | 脳神経内科外来受付 |
| 脳神経外科 | 脳神経外科外来受付 |
| 泌尿器科 | 泌尿器科外来受付 |
| 呼吸器内科 | 内科外来受付(呼吸器内科外来を予約して下さい) |
| 皮膚科 | 皮膚科外来受付 |

研究内容
ミトコンドリア異常症の病因研究
ミトコンドリア異常症は、先天代謝異常症のなかで最も頻度の高い疾患群ですが、その約半数は病因不明のままです。ミトコンドリア異常症の原因として、呼吸鎖複合体の量や集合(アセンブリー)の異常が注目されており、その検出のために極めて有用なタンパクの電気泳動法であるBlue-Native PAGEを用い、患者のスクリーニングを行っています。異常を検出した患者については、呼吸鎖複合体の構成タンパクやアセンブリーに関連する因子(アセンブリーファクター)のDNA異常の検索を行って患者の遺伝子診断を進め、正確な診断に基づいた治療法開発を他施設と共同して目指しています。
遺伝性疾患・先天異常の診断・自然歴の研究
小児神経領域には多くの遺伝性疾患・先天性疾患があり、神経合併症を有する奇形症候群等の先天異常も数多くみられます。当科では、遺伝外来と連携し、疾患の合併症や自然歴を評価し、総合的な医療管理に役立てることを目指しています。そのためには正確な診断が重要です。稀少な先天奇形疾患・遺伝性疾患に対して、アレイ検査などの新しい分子遺伝学的手法を導入して、原因不明の先天異常症候群の解析を行っています。
神経機能画像検査を用いた新しい脳機能評価法の開発のための研究
小児神経疾患では、その発達過程において認知・運動・情動的な問題を有する場合が多くみられます。従来の生理学的な手法に加えて、高精度MRIによる拡散テンソルイメージング、機能的MRIなどの複数のイメージング手法を組み合わせることにより、放射線科と共同で新たな脳機能評価法を開発するための研究を目指しています。
スタッフ
| 三牧正和 | 主任教授 |
|---|---|
| 星野英紀 | 講師 |
| 眞下 秀明 | 助手 |
| 中井まりえ | 非常勤医師 |
| 疋田敏之 | 非常勤医師 |
専門外来
その他
院内および東京都城北地区において年数回の研究会・勉強会を主催しています。
東京都城北地区の中核病院、療育病院、診療所の先生方と連携し、重症心身障害児や発達障害の診療における地域連携を目指した勉強会や研修会などに参加しています。