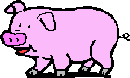 トリオールリピド(Triol lipid)
トリオールリピド(Triol lipid)
アルコール側を主としてグリセロールとする脂質(グリセロ脂質=
glycerolipid)。天然界の脂質のうち量的に圧倒的に多い。ただトリオールはグリセロールだけとは限らない。DATAはブタさんをクリック!文章の一番最後にもDATAへのボタンが有ります。
グリセロール+脂肪酸(グリセロール脂肪酸エステル)=単純脂肪質
Simple lipid(の仲間)註1=中性脂肪Neutral lipidグリセロール+脂肪酸+その他=複合脂質
Complex lipid or Compound lipidグリセロリン脂質
Glycerophospholipid(別掲)グリセロ糖脂質
Glyceroglycolipid(別掲)註1
アルコールと脂肪酸のみでできた脂質を単純脂質と呼んでいる。単純脂質群としてアルコールがモノオール、ジオール、トリオール、その他ポリオールが有り得る。グリセロール脂肪酸エステル=中性脂肪
註2脂肪酸が3分子エステル結合しているもの
註3*トリアシルグリセロール(
Triacylglycerol、TAG)*トリグリセリド(
Triglycerol、TG)註4脂肪酸が2分子エステル結合しているもの
*ジアシルグリセロール(
Diacylglycerol、DAG)*ジグリセリド(
Diglycerid)脂肪酸が1分子エステル結合しているもの
*モノアシルグリセロール(
Monoacylglycerol、MAG)*モノグリセリド(
Monoglyceride)註2
脂肪酸の定義によるがトリアセチルグリセロール(=トリアセチン)のようなものは水溶性で脂質の仲間に入れるべきではないが、構造上の相同性からデータとしては取り込むことにした。同じことはジアシルグリセロール、モノアシルグリセロールにも言える。脂肪酸の炭素鎖の長さだけでなく、グリセロール側のフリーの−OHも寄与して水溶性を示し、脂溶性を示さないものがあるが、ここではデータとして取り込んでいる。註3
脂肪(fat)という言葉が日常語として用いられている。それは時として脂質(lipid)と同義語として使用され、理解されている。即ちトリアシルグリセロールもコレステロールも一緒くたになって「脂肪の少ない食品を....」というように使われる。「時々血液の脂肪を測って....」これもコレステロールまで含めての話である。一方、「脂肪細胞」「脂肪変性」「脂肪肝」などの用語に、コレステロールを含めて考えているとは思われない。このように一般用語(俗語)として内容が曖昧になってしまった「脂肪」という用語は、「脂肪細胞」や「脂肪肝」という成熟した用語として用いる以外、学問の場では用いない方がよいのではないだろうか。付け加えていえば、組織標本作成の過程で、アルコール処理をして抜けた穴が「脂肪滴」と呼ばれたりもするが、これがトリアシルグリセロール(中性脂肪)のみならずコレステロールエステルや脂溶性ビタミンや複合脂質を含んだ場合も有り得るので、今後、形態学領域での慣用とも実態をすり合わせる必要があると考える。ついでながら、動物脂(肪)、植物油、あるいは油脂、油(あぶら)などの言葉がある。学問の世界で用いる場合は慎重に定義する必要があろう。(植田)註4
トリグリセリドは有機化学の命名法としては適切ではない。トリアシルグリセロールを教育の場では使うようにというIUPAC 、IUBの勧告は当を得たものであるが、医療のベッドサイド検査室ではトリグリセリドが通用している。これをトリアシルグルセロールに置き換えるには相当な時間がかかると思う。油脂業界ではどのようになっているのであろうか。食品業界ではモノグリが通用し、モノアシルグリセロールに変更される気配はないと聞いた。(植田)| DATA |
|---|