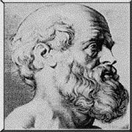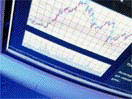|
ちょっぴりマジメな話(2):経営戦略と医学
今年の日本シリーズは王・長嶋の対決になったそうですね。 巨人ファン、また野球ファンならずとも、我々の世代は十分楽しめるように思いますが、いかがですか? さて前にもお話ししましたが、 エモリー大学の外科では毎週木曜日朝7時からGrand Roundというカンファレンスがあります。 当方が所属している移植免疫研究室だけでなく外科全体のカンファレンスで、 外科各分野の先端医療や他大学の素晴らしい教授の話が聞ける、 1時間の特別講義です。 万が一、話が自分にとって興味の浅いものでも、 講義のあとにアメリカンサイズのフリーブレックファーストが控えていますので、 当方はなるべく出席しています。 そのGrand Roundで、先日、当方にとって興味深い話がありました。 タイトルは「Reflections of a Surgical MBA」というものです。 演者はGary Bernstein MD, FACS, MBA、エモリー大学の外科の臨床助教授の方です。 今日は、その講義メモから抜粋して少しお話してみたいと思います。 当方の英語力不足から、話が断片的でわかりにくいかもしれませんがその点は御容赦ください。 また、お話の内容に伴う著作権等はすべて、前述の助教授に帰属しますので御了解ください。 お話の内容は、外科の中で必要な経営管理、戦略についてです。 タイトルにもあるMBAは、Master of Business Administrationのことで、 訳すならば、経営管理学修士号となるのでしょうか。 アメリカでは、人間の健康、生命を扱うとはいえ医療もれっきとしたサービスの一つである、 したがっていかにして合理的にそのサービスを提供するか、 またそのコストはどうか、など真剣に討論されます。 どちらかというと日本はその対局で、 生命を扱う尊い職業だから利潤追求はタブーのように考えられている側面 もあるように感じます。 どちらかが正しくてどちらかが間違いというのはありませんが、 赤字が続けば当然病院はつぶれてしまいますし、 日本の医療でも経営戦略という考え方はもう少し必要かとも思います。 さて、講義のなかでのキーワードはCore competenceです。 これは、what you do better than everyone else(他のだれよりも自分が優れているもの)で、 それがひとつあれば十分、これを決して見逃すな、ということです。 例を挙げたほうが分かりやすいかもしれません。  アトランタといえば、 コカコーラ、今や、ソフトドリンク産業のなかでは世界一です。 そのコカコーラは、 1970年代に事業拡大のため、 一時、カリフォルニアのワイナリーと映画会社のコロンビアピクチャーズを買収しました。 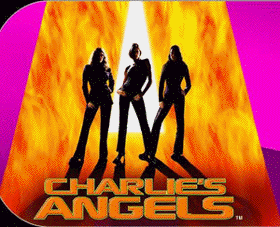 たしかにコロンビアピクチャーズは現在も映画会社として儲かっていますが、 コカコーラはその後、 世界で自分たちがすぐれているものは何かを考えたうえでこれらを手放し、 Coca-colaのみ、 ソフトドリンクのみに事業展開しました。 現在のコカコーラの繁栄の原点はここにあるのです。 さて、講義では、 経営戦略の要点として
の4つをあげていました。 次にこのleadershipについて話します。 このleadershipについては、managerではなく、leadershipの重要な役割として 
の4つがあげられていました。 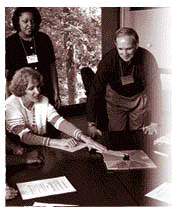 講義の中で、managerは、 「doing the right things(正しい物事を自分でしてしまう)」、 いっぽうleadershipは、 「doing the things right」、 つまりleadershipは、なんでもかんでも自分でやってしまうのではなく、 組織の人間を活用して、物事がうまく運ぶように管理する、 そのための必要な道具、手段は惜しみなく人々に与える、その分高い責任を負う・・ 例えるなら、船長さんでしょうか。 日本では一蓮托生といいますが、 英語では「we are in the same boat」といいます。 船長さんが自分でなんでもやろうとしたら、 それは大変なことですし、 部下達も「自分は信用されていないのか」といい気持ちはしません、 物事もうまくいきません。 部下、同僚を信用し万事うまく運ぶようにそのtoolを与え管理する、 当然そのためには高い決断力、責任が必要ですが。 そして自分たちの組織のなかでそのleadershipを育ててゆく・・ これは会社などの組織だけでなく、 どんな場合にもあてはまるような気がします。 地域のcommunity、家族、学校のクラスなどなど・・・ 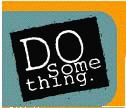 さて、講義は最後にこの言葉で閉められました。 「Do not just complain・・ ・・do something! Just do it!!(as Nike!?)」 2000.11 |
|||||