リハビリテーションの対応(Ⅱ)
| ▒ 各 論 ▒ | ||
| ⑴ はじめに | ||
| ⑵ 実際には | ||
| ⑶ 視力障害 への対応 | ||
| ⑷ 羞 明 への対応 | ||
| ⑸ 視野障害 への対応 | ||
| ⑹ 夜 盲 への対応 | ||
| ⑺ | ||
| ⑻ 総 論 へ | ||
● はじめに『ニーズの聞き取り』ありき。
ただ単に矯正視力0.5以下 → 文字が読みにくいだろうから拡大鏡処方,と安直に考えてはいけない。まず本人が何に困っているのかをきちんと把握することが必要である。ただし,「今,何に困っていますか?」と問いかけるだけでは,あいまいで不十分な結果しか得られないことが多い。
例えば,外来で眼鏡処方の際に頻繁に聞かれるのが「新聞が読みたい」という希望だったりする。これをどう捉えたらよいだろうか。日常生活で新聞が読むという行為そのものが出来ない事が,本当に問題となっているのだろうか? 自分の身として考えれば解るが,新聞を読むことはそれだけで完結している行為ではない。社会情勢や政治の動向,他者の意見を知って,その上で本当の本人の希望,やりたい事があるから読むのである。 …というのは,少々竅ち過ぎな考え方かもしれないが。
新聞を読んで,それからその人は何がしたいのかを,新聞の先にある本当のニーズを探求していく事が大事であり,それについて視覚的に困難が生じていないか検討する事は重要だと思う。外来でのロービジョン対策のひとつが,「エイド(補助具)」の取り組みであろう。
● 実際には
フリーディスカッションの中からニーズを模索していく方法よりも,ADL(Activity of Daily Living=日常生活動作)評価法などを参考に,いくつかの質問項目を用意しておいた方が時間的にも効率的に話を進めることができる。忙しい外来で聞き漏らしを未然に防ぐことができるし,本人も気づかなかった困難が見えてくる場合もある。
VF-14(下表)やVFQ-25など既存のADL評価方法をそのまま使用するのも良いが,施設によって疾患の構成比率は様々である事を考えると,既存の評価法をベースにより主要な疾患にクローズアップしたチェックポイントを独自に入れても良いと思う。例えば加齢黄斑変性が多い施設なら,読字の状況についてもう少し細かく設問を設定した方が後のエイドを用いた指導で参考になったりする。
まずこうした評価法を元に問診を行うと,優先事項としてどれから解決策を講ずるべきかが見えてくる。
例えば,本人は読書がしたいと希望しているが,それよりも生活でより重要なポジションを占める動作,例えば歩行での困難の度合いが高かったり,全体的に明るい場所での作業が困難だったりと,別の側面が見えてくる場合もある。そうした場合,平行して歩行訓練を始めたり,拡大鏡などよりも羞明の方からのアプローチの方を先行したほうが効率よくケアを進める事ができる。また,こういった質問表は同時に評価法としても活用できるので,各種エイド処方後に再度同じ質問を行う事で状況が解決できたかどうかを把握できる。
Visual Function 14( VF-14, Steinberg EP, 1994)
1 ラベル・薬のビン・電話帳といった小さな字を読む
2 新聞・本を読む
3 新聞・本の大きな活字を読む
4 近い人の顔を識別する
5 階段を見て,上り,曲がる
6 道路・交通標識・店の看板を見る
7 縫い物などの細かな家事を行う
8 チェックにサインをする
9 ビンゴ・ドミノ・カードで遊ぶ
10 ボーリング・ハンドボール・テニスなどのスポーツをする
11 調理をする
12 テレビを見る
13 昼の車の運転
14 夜の車の運転
採点方法
あなたは眼鏡をかけても 1~14の項目を行うのは困難ですか?
1)はい 2)いいえ 3)どちらともいえない
もし,はいと答えた場合,最近どの程度の困難を感じますか。
以下から選んでください。
1)少し 2)中程度 3)かなり 4)できない
注)VF-14は元々白内障患者用に開発されたもの。今は広く視覚障害者全般に適用されている。妥当性・信頼性は検討済み。ADL評価法としては,余暇活動が多く含まれているので,同じ能力低下でもADLより広い範囲の活動の評価法と見た方がよいとされている。採点法が視覚障害者の主観に基づいた評価表となっており,採点の客観性という観点からは問題がある評価法と考えられている。また,『ドミノ』や『サイン』など,日本文化とはやや表現にズレがある。特に研究目的で統計を取るなどに必要がないのであれば,より日常に用いるものに換えてしまって差し支えないのでは。
参考1) 松本憲二,他:視覚障害者に対するActivity of Daily Living(ADL)評価法.眼紀 57:411-417,2006
参考2) Steinberg EP, et al:The VF-14, An index of functional impairment in patients with cataract.Arch Ophthalmol 112:630-638,1994
参考3) english version
参考4) 前述のVFQ-25は健康関連QOLを測定する尺度として作られたNEI-VFQ(51項目)の簡略版. ☞ 関心のある人は
こちら(外部リンク)
参考5) english version
⒜中心/傍中心暗点の場合(AMD等
視野障害 として対応 ❥ 後述
⒝特に,中心や傍中心に暗点がない場合(DMR等
多くの場合,まず手元の物が見えない事に困難を感じる。
普通,教科書や新聞を読むためには0.4以上(ただし近年,各大手新聞社がフォントの拡大・改善に取り組んでおり,一律には言えないと思われる。日経が最小か?),小学生の教科書であれば,平仮名なら0.1以上,漢字であれば0.2以上の視力が必要といわれている。(湖崎 克著 「新標準近距離視力表」はんだやより)
だが,実際は0.6位の視力があっても,日常の生活で困難を訴える者もいる。繰り返しになるが,上記の視力値に拘らず,元々1.2見えていた者の視力が低下し現状に困難を感じるのであれば,それはロービジョンケアの対象になると考えた方がよい。
■「視力が出ない=大きな文字しか見えない」なら,「大きくしてしまえ,ほととぎす」である。
例えば,下の赤矢印の下,ここに何が書いてあるか読んでみてもらいたい。(簡単に読めてしまう場合,ちょっと離れた所から読んだり,+レンズで雲霧して見てみよう。)
| 帝京大学 |
何が書いてあるか,すぐには読めないでしょう?
同じ文字を,色調もそのまま拡大したものがこちら。
帝京大学
結構楽に読めてしまうのではないだろうか。
他の要因は抜きにして,単純に中心視力が低下した場合は,もちろん小さな文字を判読する事は困難になってくる。ただ,適切な倍率に拡大しさえすれば,視力がどんなに低くとも文字を読む事は理論上可能である(0.01あればなんとかなる。指数弁でも文字が読めたという報告も確かあったが,本当か?)。
■拡大方法
拡大方法にはいくつかの考え方がある。
① 相対的距離拡大法:
例えば60cmの距離で見たものを30cmで見ると,その大きさは2倍に見える。15cmなら4倍になる。実際にその物自体の大きさが変化しないにも関わらず,距離を変えたりする事でその物を大きく見せるという方法。だが,実際は誰でも15cmで対象を鮮明に見つづけることは簡単にできるわけではない。拡大鏡による補助が必要になる。
② 角度拡大法:
遠方視の場合,単眼鏡を使って見ると物体の虚像が作られるため視角が拡大するので(入射角が大きくなる),ものを大きく見ることが可能。
③ 投影式拡大法:
プロジェクターを利用してスクリーンに大きく投影したり,拡大読書器を使う方法
④ 相対的文字拡大:
対象物自体を大きくしてしまう方法。例として拡大コピーや拡大図書,拡大教科書など。場合によってコストはやや高くなる。
その人各々の困っているシチュエーションに合わせて拡大方法を選択する事が重要である。
■拡大率の決定
| 一番簡便な方法としては,倍率= | 目標視力 | で計算する方法がある。 |
| ――――――――― | ||
| 現在の視力 |
例えば,視力(0.5)あれば読める物を(0.1)の人が見るときに必要な倍率は,0.5/0.1=5倍。視力(0.05)の人だったら,0.5/0.05=10倍。
ただし,日常生活で『読む』という作業は,ほとんどが文章という文字が連続したものや,多様な背景の中から文字を拾って読むことになる。そうなってくると,じっと目を凝らして一つの視標を見て答えた結果である視力値は実際の日常的な見え方とは,人によっては必ずしもイコールではないと思う。字一つを目を凝らしてみるよりも,塊となった文章を読む方が多い。無背景のコントラスの中から目標物を読むわけではない。
だから,視力検査で(0.1)という視力値が解ったとしても,実は日常的な『視力』は(0.08)だったりして,そうすると 5倍の拡大率では実際は足りなくなる可能性がある。
このような場合,リーディングチャートを用いて読書視力を測定するとよい。有名なものでは,MN READ‐Jが汎用されている。こちらの詳細は割愛するが,これによって読書視力を計測し,最大読書速度を保って読める最小読書視力を測定する事で,より適した拡大倍率を想定する事ができる。遠/近見視力を元に倍率を考えるよりも,こちらの方が実際に拡大鏡等を処方する際に当たりがつきやすく,検査時間の大幅短縮になる。
■目的の拡大率を得るためにはどうすればよいか?
それでは,どの度数の拡大鏡が何倍になるのか?各メーカーによって倍率の計算が異なるため,『5倍の拡大率が必要だから5倍と表示のある拡大鏡』のような選び方をしてはいけない。 例えば,COIL社製Hi-Powerは16Dの拡大鏡を 5×と表記してあるが,Eschenbach社製では20Dを 5×としている。拡大鏡の倍率はメーカーによりD/4または1+D/4と異なる。同じメーカーの製品でも,低い屈折度の拡大鏡の場合はD/4で,高屈折になってくると1+D/4で計算している場合もある。 とにかく,必要倍率が決まったら各製品のdiopterを確認した上で,適切な拡大鏡を選択する事が大事である。
近見視力を測定した距離(M)×レンズの度数(D)=度数(D)の基準倍率
これで計算すると…
30cm距離で近見視力を測定→度数(D)の基準倍率は0.3×D
20Dのルーペを使うと6倍,12Dで3.6倍の効果が得られる
40cm距離での近見視力→度数(D)の基準倍率は0.25×D
20Dのルーペを使うと5倍,12Dで3倍の効果が得られる
というように,一つの拡大鏡が何倍にも化けてしまうのである。だから注意が必要。
正視の症例。30cm距離で測定した近見視力が0.1で,新聞が読みたい場合適した拡大鏡の度数は? また,同じ条件で-3.0D,+3.0Dの屈折異常がある症例の場合,それぞれ必要な度数はどうなるか。ただし,新聞を読むのに必要な視力は0.5として考える。
必要倍率は 0.5/0.1=5(倍) 正視の場合 5/0.3≒16.7(D) の屈折度が必要となる。
近視分の屈折エラーはそのままプラスのレンズが目の中に入っていると考えれば良い。極端な話,この場合だって-16.7D の強度近視の人だったら,目の中に+16.7D のレンズが入っているのと同じなので,裸眼+6cm距離で新聞が5倍になるのである。
-3.0D の屈折異常の場合だと,必要な度数は 5/0.3≒16.7 16.7-3.0=13.7(D)
このように,近視の未矯正分はうまく活用したほうがよい。眼鏡で矯正してから拡大鏡,なんてことをすると勿体無いので注意が必要。ただし,ある程度以上の乱視があると拡大しても鮮明さにかけてしまう事が多いので(乱視によってぼやけた像がそのまま拡大されてしまう),場合によっては眼鏡による矯正も併用したほうが良い。
逆に遠視の場合,未矯正であればその分拡大鏡がその度を補わなければいけなくなるので,5/0.3≒16.7 16.7+3.0=19.7(D) と更に高倍率の拡大鏡が必要になってくる。
もちろん必要な度数は以上のようになるが,ぴったりな度が製品として出ているわけではないので,この理想値を参考により使いやすいエイドを選択すること。
①近接拡大を狙った過矯正眼鏡
ロービジョンケアをやってみたいが,拡大鏡などのエイドが無いからといって,あきらめないこと。低視力 → 即,拡大鏡などのロービジョンケアグッズに目を向けるのではなく,まず屈折矯正を確実に行った上で近用眼鏡を検討すべきである。レンズセットがあれば試してみるべきだと思う。更に近見眼鏡の加入度を通常よりも上げて,近接拡大の効果を狙う事ができる。
33cmで見たものを1倍とすれば,対象物をその半分の16.5cmで見れば,視角は2倍になる。正視で調節力ゼロの人が,33cm距離のものを明視するためには+3.0D加入が必要。16.5cmを見るために+6D加入すれば2倍の拡大率が得られる。ただし,試してもらえれば解るが,近距離で長時間文字を読み続ける事,焦点距離をキープし続ける事はそんなに簡単なことではない。十分な説明を行い,理解を得た上でトライする事が重要である。また,この方法は人前でどうしても拡大鏡などの『特殊な』エイドを使いたくない人,どうしても眼鏡に固執する人にも有効である。字を書くのには作業距離が狭いため,あまり向かない。(書き文字は印字に比べて大きいため,必ずしも読字がしやすい拡大率まで拡大する必要は無い。本人に適した筆記用具の選択,またはタイポスコープを使用することで近用眼鏡だけでも対応できる場合もある。)
②拡大鏡
大きく分けて,手持ち式と卓上式の二つが挙げられる。それぞれ照明付きの物も選択できる。
手持ち式は持ち運びに適したものが多く,様々な利用方法が考えられる。焦点距離を自分でキープしなければならず,人によっては使用困難な場合もある。片手がルーペの保持で塞がってしまう。
それに対して卓上型は焦点距離が一定に保たれているため,両手も開いて楽ではあるが,実はスタンドの高さ=焦点距離ではない。大体の場合焦点距離よりも短くスタンドが設定してあるため,正視の場合は調節するか,近見矯正が必要。少し持ち上げれば焦点が合うが,それでは不便だし実用的ではない。
なぜ焦点距離にスタンドの高さを合わせないのか,メーカーに聞いてみたが理由がはっきりしない。一番言われているのが,もし焦点距離の高さに設定すると,日のあたるところに放置する事で発火する危険性があるから,というもの。本当??
アクリルの素材などを使って,自分で焦点距離に合わせて脚を足してしまうというのも一つの手である。
照明は,拡大率が大きい拡大鏡ほど焦点距離が狭まり,視界が暗くなってしまうため必要となる場合が多い。最近ではLEDを使用したモノが主流。長時間使用可能で軽量である。もしくは,他のデスクライトなどの照明をうまく活用することで,かなり視環境は改善する。
 |
 |
 |
| 手持ち式拡大鏡 | 照明付き手持ち式拡大鏡 | 照明付き卓上型拡大鏡 |
③拡大読書器
実は拡大鏡や他のエイドを凌いで,多くの人が1度使うと希望を持つようになるのが,この拡大読書器である。
基本的な操作はスイッチを入れて,カメラの下に見たいものを入れるだけで,あとは画面に拡大した映像が映し出される。何より一番のメリットは黒白反転機能などで羞明を軽減し,コントラストを向上させる機能があることだ。使う人各々が自分の一番見やすい状況に画面をカスタマイズする事ができるのは,他のエイドにはない機能である。
ところで,ティッシュを用意してそれを目の前に広げて透かすようにして,下の図を見てみよう。
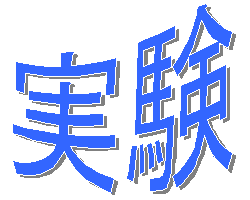
ティッシュによっては2枚重ねを剥がして1枚にして見てみよう。ちょっとした霧視のシミュレーションになる。
どちらの背景が見易いだろうか? もちろん両方ともフォントは同じである。
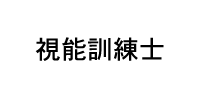 |
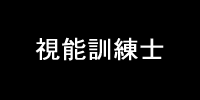 |
黒地バックの方が結構すんなり目に入ってくるのがわかるでしょうか?
同じ視力でも,羞明を抑える事によって,より見易い環境を作る事ができる。拡大読書器の機種によっては他にも青黄に変換するものもある。
拡大読書器の操作は,実際は一概に簡単とは言いきれない。処方してそれでおしまい,というものではない。単語ではなく新聞や本のような文章を読むときは,台や紙面の動かし方,適切な大きさに拡大する方法などにコツがいるので,闇雲に動かしていると人によっては車酔いのような症状が出る事もある。ナイツから出ている拡大読書器練習マニュアルなどを参考に,その人の障害に合った操作方法を教える事,もしくは各地で開催されている講習会などを積極的に利用することが大事である。
また,機種によっても機能がかなり異なるので,その人が生活のどのシーンで,何を見るためにそれを使うか,しっかり考慮した上で,実際に操作も試してもらいつつ選ぶ事が重要である。日常生活用具として申請した場合,耐用年数が8年間なので,値段も考えるとそう簡単には買い換えられない。
使い方さえマスターしてしまえば,あとは変幻自在で,これを使って字を書いたり,絵を描いたり,染物をしたり,爪を切ったりと考え様によっては色々使える物である。
Mここで羞明が,2か所に出てきた.低視力と羞明は,透光体・視細胞に起因するものとして相互に関連することになる.低視力対応すなわち羞明対応,といった面が大きい.
バリアフリーの取り組みでは,視認性,可読性,色彩調和,といった観点になる.視認性とは,上記のように黒背景で黄色がすぐれている.可読性とは,黒のような収縮色が画数の多い文字で有利である,などという心理要素に配慮するスタンスである.
M関心のある人は外部リンクへ
⏎次へ
対象物を見やすいように拡大することはもちろん大事だ。しかし,全てを拡大して見る事を頑張るだけでは疲れてしまう。ほんの少しの工夫で身の回りのものがぐっと使いやすくなる事がある。
その他,ロービジョン者にとって使いやすい物は,実は色々なところに転がっている。近所のスーパーやホームセンターで,当事者の気持ちになって商品を眺めてみてほしい。あのような状況だったら,これが使いやすいのではないか,といった物が結構見つかるはずである。ロービジョン者本人は,どうしても自分で使いやすい物を積極的に探す事が難しい場合が多い。ロービジョン眼鏡店や便利グッズのサイトに商品を注文することだって困難な場合が多い(そして,そういった所の商品は正規の値段なので少々高かったりもする!)。近所のどこでこれが手に入る,といった情報を提供することも大事だと思う。
![]()
2008
【プリントアウトは縮小80%を推奨】